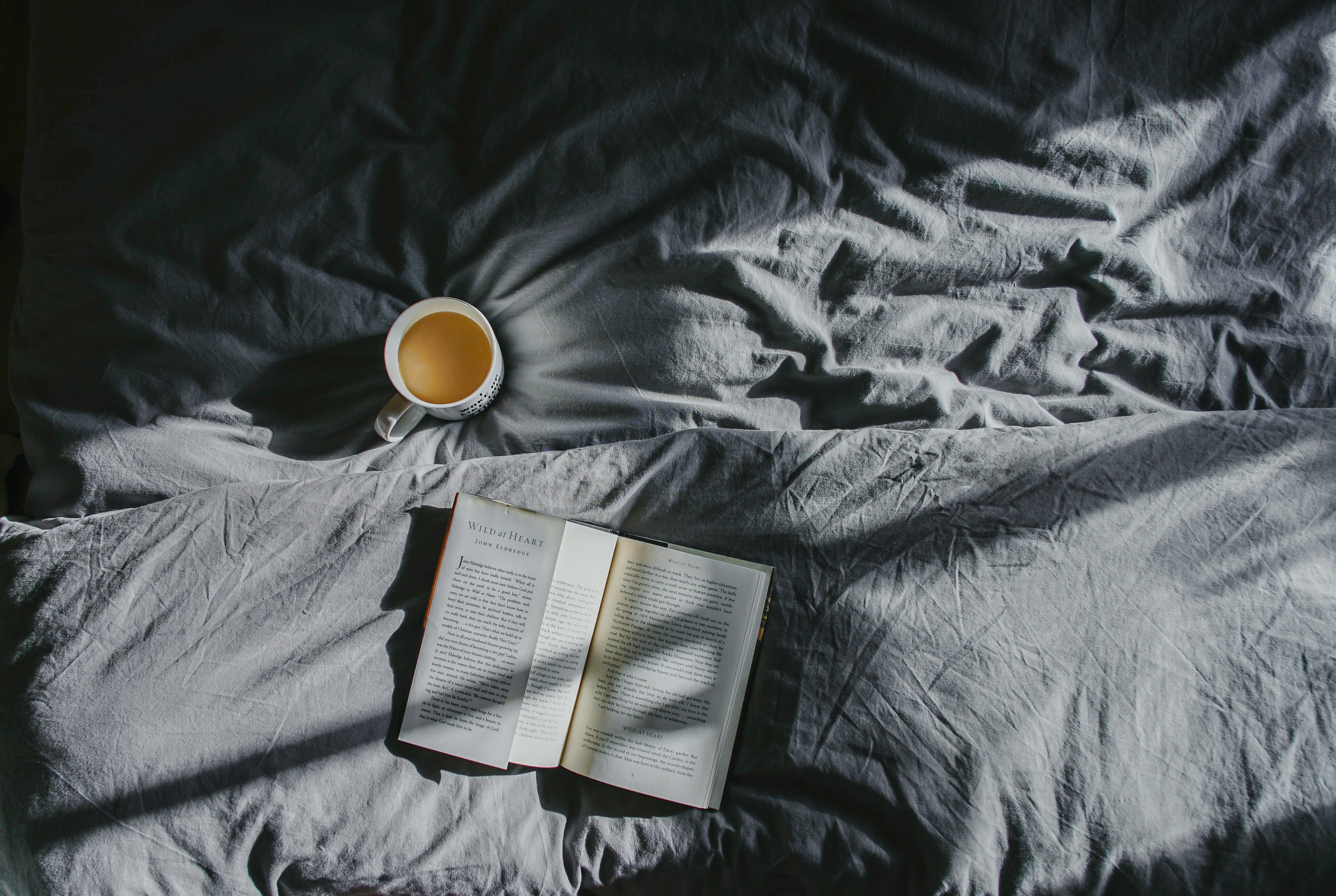小学生が片付けない理由と親のイライラを減らす神アイデア7選

お子さんが小学生になり、成長の喜びを感じる一方で、「何度言っても片付けない!」と、片付けをめぐってイライラしたり、頭を悩ませるママは少なくないのではないでしょうか?
「どうしてうちの子はいつも片付けられないんだろう?」と、つい叱ってしまったり、ため息をついてしまうこともあるかもしれませんね。
でも、安心してください。片付けが苦手なのは、お子さんの性格ややる気の問題だけではないことがほとんどです。実は、小学生の子どもたちが片付けないのには、ちゃんとした理由があるのです。
このブログでは、小学生の子どもたちがなぜ片付けないのか、その理由を深く理解し、親のイライラを減らすための具体的な方法や、子どもが自分から片付けたくなるような「神アイデア」を7つご紹介します。
家族みんなが笑顔で過ごせる快適なリビングや子ども部屋を作るヒントを一緒に見つけていきましょう。
小学生が片付けない理由。子どもの気持ちと行動を理解しよう

「早く片付けなさい!」そう言っても、一向に子ども部屋がきれいにならない、リビングにおもちゃが散らかったまま…そんな状況に、毎日うんざりしているお母さんもいるかもしれません。
しかし、小学生の子どもたちが片付けないのには、いくつかの主な理由があります。
小学生が部屋を片付けない、主な理由を徹底解説
1. 優先順位が低いから
子どもにとって、遊びや勉強、好きなことに集中する時間はとても大切です。
その一方で、片付けは「やらなければならないこと」であり、どうしても優先順位が低くなりがちです。特に、遊びに夢中になっている時は、片付けという行為に意識が向きにくいものです。
2. 片付け方がわからないから
大人が「片付けなさい」と言っても、子どもは具体的にどうすればいいのか、どこに何をしまえばいいのかが明確にわかっていないことがあります。
「片付ける」という行動は、実は多くの工程を含んでいます。例えば、「これはどこにしまう?」「これは必要?捨てる?」「この山をどうすればいい?」といった判断が苦手な子もいるのです。
特にモノが多い部屋だと、どこから手をつけていいか分からなくなり、やる気を失ってしまうこともあります。
3. 空間認識能力や計画性が未発達だから
小学生、特に低学年のうちは、まだ空間認識能力や計画性を司る脳の発達が途上にあります
例えば、ボックスにきれいに収めるには、物の大きさや形を把握し、空間をどう使うかを考える必要があります。
また、散らかった部屋全体をどのように整理していけば良いか、段取りを立てるのも難しいのです。大人のように、「ここまで片付けたら終わり」という見通しを立てるのが苦手なため、途中で飽きてしまうこともあります。

4. 片付けのメリットを感じにくいから
大人であれば、部屋がきれいになると心が落ち着く、探し物が減る、といったメリットを感じられますが、子どもにとっては、そのメリットを実感しにくいものです。
むしろ、片付けに時間を取られることで、遊びの時間が減る、と感じてしまうこともあります。片付けが「やらされ仕事」になっていると、自主的な行動にはつながりません。
5. モノが多すぎるから
これも非常に大きな理由です。誕生日やクリスマス、イベントごとにもらうおもちゃや文房具が増え、いつの間にか子ども部屋やリビングがモノで溢れていませんか?
収納スペース以上にモノがあると、どこにしまっても収まりきらず、結局散らかる原因になります。親子で一緒にモノの量を定期的に見直す必要があります。
これらの理由を理解することで、お子さんが「どうして片付けないの?」とイライラする前に、具体的な対策を考える第一歩になります。
子供が『片付けられない子』になる背景・発達段階の関係
子どもが「片付けられない子」になる背景には、その子の発達段階が大きく関係しています。
大人にとっては簡単な片付けも、子どもにとっては複雑なスキルを必要とする行動なのです。
年齢による発達段階の違い
-1024x576.jpg)
- 幼児期(〜小学校低学年):
この時期は、まだ抽象的な思考や論理的な思考が未熟です。
目の前にあるモノを一つずつ認識することはできても、それらを分類したり、適切な場所に戻すという一連の作業は非常に難しいと感じます。
おもちゃを遊んだ後、すぐに次の遊びに移ってしまうのは、切り替えが苦手なことや、遊びへの関心が片付けよりもはるかに大きいからです。
また、集中力の持続時間も短いため、途中で飽きてしまうこともよくあります。 - 小学校中学年〜高学年:
空間認識能力や計画性が少しずつ発達してきますが、それでも大人と比べるとまだまだ未熟です。
物の大切さや、整理整頓のメリットを理解し始める時期ではありますが、具体的な方法や、常に意識して行動する習慣が身についているわけではありません。
この時期になると、友達との関係や学校生活など、片付け以外のことに意識が向き始めることも、片付けが進まない理由の一つになることがあります。
「自分でやりたい」と「できない」のジレンマ
子どもは成長するにつれて、「自分でやりたい」という自立心が芽生えます。
しかし、片付けに関しては「自分でやりたい」という気持ちがあっても、実際にどうすれば良いのかが分からなかったり、まだその行動が難しいことがあります。
結果として、親が手を出してしまったり、叱ってしまったりすることで、子どものやる気を損ねてしまうことも少なくありません。
親の言葉かけの影響
「何度言ったらわかるの!」「また散らかして!」といったネガティブな言葉は、子どもの自己肯定感を下げ、片付けへの苦手意識を強めてしまいます。
親がいつもイライラした様子で片付けを促すと、子どもは片付けそのものに嫌な感情を抱くようになり、余計に「片付けない子」になってしまう可能性があります。
子どもの成長と発達段階を理解し、その上で適切なサポートをすることが、片付けを習慣化させるための大切な一歩となります。
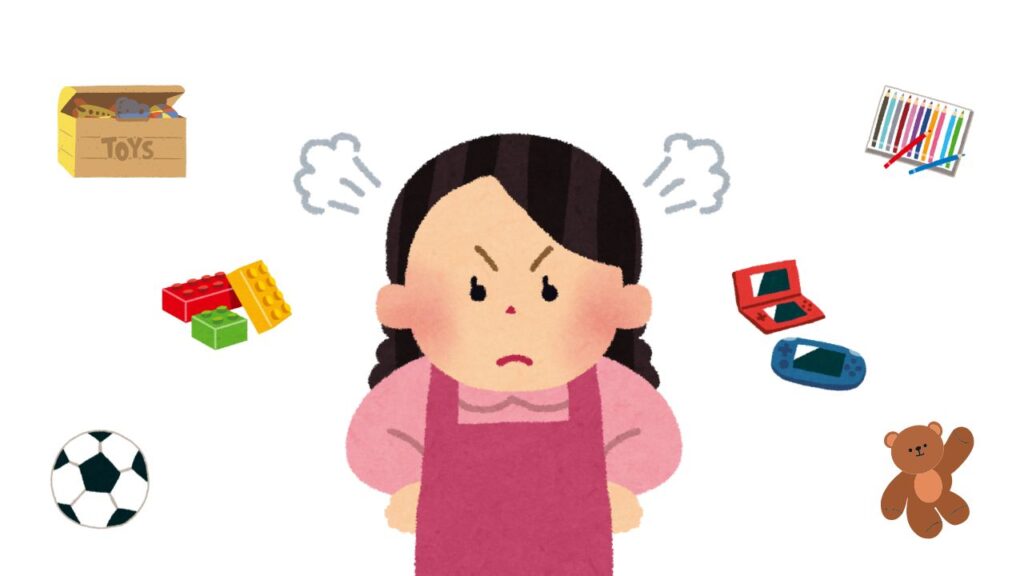
親が知っておくべき!発達障害と片付けられない可能性
お子さんが「何度言っても片付けない」「他の子と比べて片付けが極端に苦手」と感じる場合、発達障害の可能性も視野に入れる必要があるかもしれません。
もちろん、全ての片付けが苦手な子が発達障害であるわけではありませんが、もし心配な点があれば、専門機関に相談することも大切です。
発達障害の中でも、特に片付けの苦手さと関連が深いとされるのが以下の特性です。
ADHD(注意欠陥・多動性障害)
- こだわりの特性: 特定の並び方や収納方法にこだわりがあり、少しでも崩れると混乱してしまうことがあります。
逆に、自分なりのルールが強すぎて、家族と片付けの認識が異なることもあります。 - 臨機応変な対応の苦手さ: 状況に応じて柔軟に対応することが苦手なため、「片付けなさい」という漠然とした指示ではどうしていいか分からず、フリーズしてしまうことがあります。
具体的な指示がないと動けない場合があります。 - 感覚過敏: 物の触感や匂い、見た目のごちゃごちゃ感に過敏に反応し、片付けをすることがストレスに感じられることもあります。
これらの特性がある場合、いくら「頑張りなさい」と叱っても、子どもにとっては非常に難しい課題となります。
叱責は、子どもの自己肯定感を下げるだけでなく、親子関係にも悪影響を及ぼしかねません。
もし、以下のような状況が慢性的に見られる場合は、一度専門家(小児科、児童精神科、発達支援センターなど)に相談してみることを検討してください。
- 学年が上がっても片付けの様子が全く改善されない
- 片付け以外の面でも、集中力や行動面で気になる点がある
- 特定の物や行動への強いこだわりがある
- 「何度言っても理解してくれない」と感じることが多い
発達障害と診断されたとしても、それは「できない」のではなく、「脳の特性上、苦手な部分がある」ということです。
適切なサポートや環境調整を行うことで、子どもは大きく成長することができます。親御さん自身も、お子さんの特性を理解することで、イライラが減り、より効果的な子育てができるようになるでしょう。
親がイライラしてしまう本当の原因と心の対策

「どうしてうちの子はこんなに片付けないの!?」と、親であるあなたがイライラしてしまう気持ち、とてもよく分かります。
でも、そのイライラの本当の原因は、もしかしたらお子さんの行動だけではないかもしれません。
『何度言っても片付けない!』親のイライラが増す悪循環とは
小学生の子どもが片付けない時、親がイライラしてしまうのは、当然の感情です。しかし、そのイライラが募り、悪循環に陥ってしまうことがあります。
1. 親の期待と現実のギャップ
「小学生になれば、ある程度自分でできるようになるはず」「何度か教えれば、もう覚えているはず」といった、親の期待がお子さんの現状と食い違う時、イライラは生まれやすくなります。
親としては、これまで教えてきたことが身についていないように感じ、裏切られたような気持ちになることもあるでしょう。
2. 終わりが見えない家事の負担
片付けない子どものせいで、いつまで経っても部屋が散らかったまま、探し物が増える、掃除がしにくい…といった状況は、親の家事負担を増大させます。
日々の忙しい生活の中で、これ以上仕事が増えることに、心理的なストレスを感じるのは当然です。特にママは、家の中の秩序を保つ役割を無意識に背負ってしまいがちです。
3. 「しつけ」への焦り
「このままだとだらしない大人になってしまうのではないか」「ちゃんとしたしつけができていないと思われるのではないか」といった焦りも、親のイライラを増幅させます。
片付けられないことが、まるで子育ての失敗のように感じられ、自信を失ってしまうこともあるでしょう。

4. 過去の経験や自分の基準
自分自身が幼い頃からきちんと片付けができていた、あるいは親から厳しくしつけられた、といった経験があると、子どもが片付けられないことに過剰に反応してしまうことがあります。
自分の基準を子どもに当てはめてしまい、できない子どもに対して「どうしてできないの?」という気持ちが湧いてきてしまうのです。
5. 繰り返しの注意による疲弊
「何度言っても片付けない」という状況が続くと、親は同じことを言い続けることに疲弊し、精神的に消耗してしまいます。その疲弊感が、さらにイライラを募らせる原因となります。
このような悪循環が生まれると、親は感情的に子どもを叱ってしまいがちになります。しかし、感情的な叱責は、子どものやる気を奪い、片付けへの苦手意識をさらに強めてしまう可能性があります。
結果として、子どもはますます片付けから遠ざかり、親のイライラは増すばかり…という負のスパイラルに陥ってしまうのです。
この悪循環を断ち切るためには、まず親自身が、なぜ自分がイライラしているのか、その本当の原因を理解することが大切です。
「捨てるよ」「は逆効果」片付けない子どもへのNGワード・接し方

子どもが片付けない時、つい言ってしまうNGワードや、逆効果になる接し方があります。
これらの言葉や態度は、子どものやる気を奪い、かえって片付けへの苦手意識を強めてしまうため注意が必要です。
NGワード集
- 「こんなに散らかして、もう捨てるよ!」
- 理由: 子どもにとって、おもちゃや持ち物は大切なものです。捨てるという言葉は、子どもに恐怖心を与え、親への不信感につながる可能性があります。
また、「捨てられる」ことで、モノを大切にしない態度を助長したり、隠れてモノを溜め込む原因になることもあります。
- 理由: 子どもにとって、おもちゃや持ち物は大切なものです。捨てるという言葉は、子どもに恐怖心を与え、親への不信感につながる可能性があります。
- 「何度言ったらわかるの!」「いい加減にしなさい!」
- 理由: 感情的な言葉は、子どもを萎縮させ、自己肯定感を下げます。子どもは「また怒られる」と感じ、片付けそのものにネガティブな感情を抱くようになります。
具体的な行動を促すのではなく、ただ叱られていると感じるだけになりがちです。
- 理由: 感情的な言葉は、子どもを萎縮させ、自己肯定感を下げます。子どもは「また怒られる」と感じ、片付けそのものにネガティブな感情を抱くようになります。
- 「どうして〇〇ちゃんはできるのに、あなたはできないの?」
- 理由: 他の子どもと比較することは、子どもの劣等感を刺激し、自信を失わせます。子どもは「自分はダメな子だ」と感じ、片付けだけでなく、他のことにも意欲をなくしてしまう可能性があります。
- 「早く片付けないと、おやつなしだよ!」
- 理由: 報酬や罰で片付けをさせようとすると、子どもは「おやつが欲しいから片付ける」というように、片付けの本当の意味を理解できなくなります。自発的な行動にはつながりにくく、親が見ていないところでは片付けない、という状況を生む可能性があります。
- 「もうママが全部やっちゃうからいい!」
- 理由: 親が全てやってしまうと、子どもは「結局ママがやってくれるから大丈夫」と思い、自分で片付ける機会を失います。自分で片付ける習慣が身につかず、いつまでも親に頼ってしまうことになります。
逆効果になる接し方
- 感情的に怒鳴る、叱る: 親が感情的になると、子どもは萎縮するか反発するかです。冷静に、具体的な指示を出すことが大切です。
- 完璧を求めすぎる: 子どもが片付けた時に、少しでも乱れているとすぐに直したり、注意したりすると、子どもは「どうせやっても怒られる」と感じ、やる気をなくしてしまいます。まずは「できた」ことを認めましょう。
- 片付けのルールが曖昧: 「片付けなさい」というだけでは、子どもは何をどこにどう片付ければいいか分かりません。具体的な場所や方法を明確にすることが必要です。
- 親自身が片付けない: 親の行動は、子どもにとって一番のお手本です。親の部屋や共有スペースが散らかっていると、子どもは「ママも片付けないから、自分も片付けなくていいや」と思ってしまいます。
これらのNGワードや接し方を意識的に避けることで、子どもの片付けへの意識をポジティブな方向に変え、親子のストレスを大きく減らすことができます。
親子のストレスを減らすための心構えと共感のコツ

片付けをめぐる親子のバトルは、親にとっても子どもにとっても大きなストレス源です。
このストレスを減らし、穏やかな親子関係を築くためには、親の心構えと、子どもへの共感の仕方が鍵となります。
1. 親自身の「完璧主義」を手放す
「部屋は常にきれいに保たれるべき」「全てのモノは指定の位置にあるべき」といった完璧主義的な思考は、時に親自身を苦しめます。
子どもが完璧に片付けられないのは当たり前、というおおらかな気持ちを持つことが大切です。多少散らかっていても、許容できる範囲を広げることで、イライラを減らすことができます。
2. 子どもの発達段階を理解する
「なぜ片付けられないのか?」の項目でも触れましたが、子どもには子どもの発達段階があります。
大人と同じレベルで片付けができるはずがない、ということを理解し、焦らず、長い目で見て成長をサポートする視点を持つことが重要です。

3. 片付け以外の「良い点」に目を向ける
子どもが片付けないことにばかり注目してしまうと、親も子どもも疲弊します。
片付け以外の、例えば「今日は学校でこんなに頑張ったね」「お友達に優しくできたね」など、子どもの良い行動や成長に目を向け、それを言葉にして伝えることで、親子の関係性が良好になり、結果的に子どものやる気にもつながることがあります。
4. 休憩も大切!親自身のストレスケア
子育ては忍耐と体力が必要です。親自身がストレスを抱え込んでいると、些細なことでもイライラしやすくなります。
時には一人の時間を作ったり、好きなことをする時間を持つなど、親自身の心と体を休ませることも非常に重要です。
共感のコツ

- 子どもの気持ちを言葉にする(Iメッセージ):「大変だったね」「疲れたね」
- 例:「遊びに夢中になって、片付けたくない気持ち、わかるよ。」
- 「たくさんのモノを片付けるの、大変だよね。」
- 「もう眠いのに、片付けするのは嫌だよね。」
- このように、まず子どもの感情に寄り添い、共感する言葉をかけることで、子どもは「ママは自分の気持ちを分かってくれている」と感じ、心を開きやすくなります。
- 「〜したかったんだね」と、意図を汲む
- 例:「もっと遊びたかったんだね。」
- 「このおもちゃ、まだ使うつもりだったんだね。」
- 子どもの行動の裏にある気持ちを想像し、言葉にすることで、子どもは理解されたと感じ、次の行動に移りやすくなります。
- まずは子どもの言い分を聞く
- 頭ごなしに「片付けなさい!」と言うのではなく、「どうしたの?」「何か困っていることある?」と、子どもの言い分や状況を一度聞いてみましょう。意外な理由が見つかるかもしれません。
- 「もしよかったら、ママが少し手伝おうか?」
- 共感した上で、具体的な手助けを提案することで、子どもは「一人じゃない」と感じ、片付けへのハードルが下がります。ただし、あくまで「手伝う」姿勢を忘れずに、全てをやってしまわないように注意が必要です
片付けをめぐる親子バトル!家庭でよくある失敗例とその対策

「うちだけじゃないんだ…」と、多くのご家庭で片付けをめぐる親子バトルが繰り広げられていることでしょう。
ここでは、実際に家庭でよくある失敗例とその対策をご紹介します。他のご家庭の体験談に学ぶことで、ご自身の家庭での対策のヒントを見つけてみてください。
片付けない子供へのしつけでよくあるトラブル・事例集
片付けない子どもへのしつけは、親にとって本当に悩ましい問題です。
良かれと思ってやったことが、かえって逆効果になってしまうこともあります。ここでは、家庭でよくあるトラブル事例と、その背後にある心理、そして対策を考えます。
事例1:親が「捨てるよ!」と言い、子どもが泣き叫ぶ
- 状況: リビングにおもちゃが散乱し、何度言っても片付けない息子(小1)に、ママが「もういらないなら、全部捨てるよ!」と怒鳴ってしまった。息子は大泣きし、余計に片付けを拒否。
- 子どもの心理: 大切なおもちゃを取られる恐怖、ママへの不信感。「どうせ捨てられるなら、片付けても無駄」という諦め。
- 親の心理: 早く片付けてほしい、言うことを聞いてほしい、という焦りや怒り。
- 対策:
- 「捨てる」という言葉は使わない: 代わりに「使わないおもちゃは、しばらく箱にしまっておこうか」「ここに入りきらないものは、別の場所に移す?」など、具体的な代替案を提示する。
- 本当に不要なものは一緒に確認: 親が勝手に捨てるのではなく、子どもと一緒に「これはもう遊ばないかな?」と確認し、納得した上で処分する。
- 選択肢を与える: 「今日中に片付けないと、明日まで遊べないよ」など、行動の結果を事前に伝えることで、子どもに選択と責任を持たせる。
事例2:親が結局全部片付けてしまい、子どもが何もしなくなる
- 状況: 遊びに夢中の娘(小3)に「片付けなさい」と何度言っても聞かず、諦めたママが結局一人で全て片付けてしまう。結果、娘はいつも片付けを親任せに。
- 子どもの心理: 「どうせママがやってくれるから大丈夫」「片付けはママの仕事」という依存心。
- 親の心理: 早く部屋をきれいにしたい、片付けられない自分へのイライラ、面倒な気持ち。
- 対策:
- 「手伝う」姿勢を徹底する: 「一緒にやろう」「ママがここをやるから、あなたはここをお願い」と、あくまで「一緒」に行動する。
- 片付けのゴールを明確に: 「このおもちゃだけ、箱に戻そうね」など、子どもにもできる小さなタスクを与える。
- 結果を受け止める: 子どもが片付けなかった場合は、その結果(例えば、散らかったままだと友達が遊びに来られない、探し物が見つからないなど)を体験させることも必要。ただし、怒るのではなく、淡々と事実を伝える。
事例3:片付けのルールが曖昧で、いつも同じ場所が散らかる
- 状況: 「片付けなさい」とは言うものの、どこに何をしまえば良いのか、具体的な場所が曖昧なため、いつもリビングの特定の場所(ソファの上、テーブルの下など)におもちゃや本が山積みに。
- 子どもの心理: どこに置けば良いか分からない、考えるのが面倒。
- 親の心理: いつも同じ場所が散らかることへの諦めや苛立ち。
- 対策:
- モノの定位置を決める: おもちゃの種類ごとにボックスを用意したり、本棚の場所を決めたりと、具体的な収納場所を親子で一緒に決める。
- ラベルや写真で視覚化: 文字が読めない幼児や、整理が苦手な子には、ボックスに写真やイラストのラベルを貼ることで、どこに何をしまうかが一目でわかるように工夫する。
- 収納場所を使いやすく: 子どもが自分で出し入れしやすい高さや場所に収納を作る。
これらの事例から学べることは、子どもへの声かけや接し方、そして環境作りが非常に重要だということです。
一方的に叱るだけでなく、子どもの気持ちを理解し、具体的な解決策を「一緒」に見つけることが、トラブル解決の鍵となります。
『片付けない娘にイライラ』体験談に学ぶ、言ってはいけない言葉
多くの親が経験する「片付けない子どもへのイライラ」。私自身も、娘の片付けに関して頭を抱えることがよくありました。
ここでは、私の失敗談を交えながら、言ってはいけない言葉と、代わりに効果的だった言葉をご紹介します。
私の失敗談:リビングが動物園状態!

娘が小学校に入学したばかりの頃、リビングでブロック遊びをするのが日課でした。遊び終わると、なぜかブロックはいつもリビングに散らかったまま。
リビングはまるで動物園のような状態に。私が「片付けてね!」と言うと、「後でやる〜!」と返事をするものの、一向に片付けは始まりません。しまいには、「ママが片付ければいいじゃん!」と反抗する始末。
私も仕事と家事に追われ、へとへと。「どうして、こんな簡単なことができないの!?」「ママは疲れているのに、なんで手伝ってくれないの!?」とイライラが募り、ついに言ってしまいました。
「もう!そんなに片付けないなら、そのブロック全部ゴミ箱に捨てるからね!もう買わないから!」
娘は、私の剣幕に大泣き。私も後悔の念にかられました。結局、その日は私が半ば感情的に片付け、娘はさらに私に反発するようになり、片付けはますます進まなくなりました。
言ってはいけない言葉とその理由
この体験から学んだ、特に言ってはいけない言葉は以下の通りです。
- 「ゴミ箱に捨てるよ!」「もう捨てたから!」
- 理由: 子どもにとってモノは、単なる「物」ではありません。思い出や愛着が詰まった大切な存在です。それを「捨てる」と脅すことは、子どもの心を深く傷つけ、親への不信感を植え付けます。また、「どうせ捨てられるなら…」と、モノを大切にしない気持ちや、隠して持ち続ける原因にもなります。
- 「本当に使わないの?」「もういらないんでしょ!」と責める
- 理由: 決めつけるような言葉は、子どもを追い詰めてしまいます。子どもはまだ、いる・いらないの判断基準が曖昧なことも多く、親に責められると反発するか、諦めてしまいます。
- 「いい加減にしなさい!」「何度言わせるの!」
- 理由: 感情的な言葉は、子どもに恐怖心を与えるだけで、具体的な行動にはつながりません。ただただ「怒られている」と感じ、片付けへの嫌悪感を募らせるだけです。
- 「なんでこんなに散らかすの?」「どうしてできないの?」
- 理由: 質問の形をとっていますが、これは非難の言葉です。子どもは「自分はダメな子だ」と感じ、自己肯定感が低下します。なぜ片付けられないのか、子ども自身も分かっていないことが多いのです。
代わりに効果的だった言葉

私の失敗から学び、試行錯誤の末、効果があったと感じる言葉かけは以下の通りです。
- 「〇〇(モノの名前)は、どこに帰る場所だったかな?」
- モノに「お家」という表現を使うことで、片付けをゲームのように楽しく、具体的に促すことができます。
- 「あと〇分で片付けタイムだよ。それまでに、あと何して遊びたい?」
- 片付けの時間を明確にすることで、見通しを持たせ、心の準備をさせます。また、遊びの時間を尊重する姿勢を見せることで、子どもは納得しやすくなります。
- 「ママも一緒に手伝うから、〇〇(モノの名前)をこっちのボックスに入れてくれる?」
- 「一緒に」という言葉は、子どもに安心感を与え、協力を促します。具体的な指示を出すことで、何をすれば良いかが明確になり、行動しやすくなります。
- 「〇〇が片付けてくれたら、もっと広く遊べるようになるね!」
- 片付けのメリットを具体的に伝え、子ども自身が片付けの必要性を感じるように促します。
- 「わぁ、きれいに片付けられたね!ありがとう、助かったー!」
- 片付けができた時には、結果だけでなく、その行動自体を具体的に褒めることが大切です。感謝の気持ちを伝えることで、子どものやる気は大きく向上します。
親の言葉一つで、子どもの行動は大きく変わります。イライラする気持ちは一旦置いて、ポジティブで具体的な言葉かけを意識することが、片付けバトルを減らす第一歩です。
子供が自分で片付けたくなる!習慣づけとやる気を引き出す工夫

「片付けなさい!」と毎日言い続けるのは、親も子どもも疲れてしまいますよね。
大切なのは、子どもが「自分で片付けたくなる」ような環境を作り、習慣づけていくことです。ここでは、そのための具体的な工夫をご紹介します。
「最初が肝心!」片付けられる子どもに育てる習慣化の方法
子どもの片付け習慣を身につけさせるには、「最初が肝心」です。幼い頃からのアプローチが、その後の片付けに対する意識を大きく左右します。
1. モノの量を「子どもの管理能力」に合わせる
最も重要なのは、子どもの管理できるモノの量に合わせることです。収納スペースに収まりきらないほどのモノがあると、子どもは片付けようにも片付けられません
- 定期的な見直し: 誕生日やクリスマスなどのイベント後には、必ずおもちゃや本の見直しを行う習慣をつけましょう。「増えたら減らす」というルールを家族で共有することが大切です。
- 親が手本を見せる: 親自身が自分のモノを定期的に整理し、必要なモノだけを持つ姿勢を見せることで、子どもも自然とモノの管理を意識するようになります。
2. モノの「定位置」を明確にする
「どこに何をしまえばいいのか」が明確でないと、子どもは片付けることができません
- 具体的に示す: おもちゃの種類ごとにボックスを用意したり、本の場所、文房具の引き出しなど、細かく定位置を決めてあげましょう。
- 視覚的に分かりやすく: 幼児や低学年の子どもには、ボックスに写真やイラストのラベルを貼るのが非常に効果的です。文字が読めるようになっても、視覚的に分かりやすい工夫は有効です。
- 「モノのお家」という表現: 「このおもちゃは、ここがお家だよ」というように、擬人化した言葉を使うと、子どもは遊び感覚で片付けに取り組めることがあります。
3. 収納場所を「使いやすく」する
どんなに定位置を決めても、子どもにとって使いにくい場所では習慣化しません。
- 子どもの目線で: 子どもが自分で出し入れしやすい高さ、手の届きやすい場所に収納スペースを作りましょう。重たいボックスは下に、軽いものは上に配置するなど、工夫が必要です。
- シンプルで簡単な収納: 複雑な仕組みの収納よりも、ポンと入れるだけで済むようなシンプルなボックス収納などが、子どもには続けやすいです。
- 「使ったら戻す」を徹底: 「使ったら元の場所に戻す」というワンアクションを意識させることで、散らかる前に片付ける習慣が身につきます。
4. 片付けを「生活の一部」に組み込む
特別な時間としてではなく、日常のルーティンに片付けを組み込むことが大切です。
- 寝る前、食前の習慣化: 「寝る前5分は片付けタイム」「ごはんを食べる前に、リビングのおもちゃを片付けよう」など、時間を区切って習慣化します。
- 「終わりの時間」を決める: 遊び始める時に「〇時になったら、お片付けだよ」と声をかけ、遊びの終わりと片付けの始まりを意識させます。
5. スモールステップで「成功体験」を積ませる
最初から完璧を求めず、小さな成功体験を積み重ねることがやる気につながります。
- 目標を小さく設定: 「全部片付けなさい」ではなく、「このブロックだけ箱に入れよう」「絵本だけ棚に戻そう」など、子どもでも簡単にできる目標から始めます。
- できたことを具体的に褒める: 「よくできたね!」「このおもちゃ、きれいに片付いたね!」と、具体的に褒めることで、子どもは達成感を感じ、次も頑張ろうという気持ちになります。
「最初が肝心」なこの時期に、親が焦らず、根気強くサポートすることで、子どもは楽しみながら片付けの習慣を身につけていくことができます。
コツは一緒に!親子でできる片付け・整理整頓トレーニング

子どもが片付けを習慣化するためには、親が「一緒に」取り組むことが非常に効果的です。
単に指示を出すだけでなく、親が手本を見せ、サポートすることで、子どもは片付けのスキルを学び、やる気を引き出すことができます。
1. 「一緒に」片付けタイムを設ける
- 家族全員で: 片付けは子どもだけの仕事ではありません。家族全員で「今日は〇時まで、みんなで片付けよう!」と時間を決め、それぞれの持ち場を片付けます。パパやママも自分のモノを片付ける姿を見せることで、子どもも「自分も頑張ろう」という気持ちになります。
- 役割分担: 「ママはここの書類を整理するから、あなたはここにおもちゃを戻してくれる?」と具体的な役割分担をすることで、子どもも自分の仕事が明確になり、責任感を持って取り組めます。
- 声かけと手助け: 子どもが困っている様子があれば、「どこから手伝おうか?」「どうしたらいいと思う?」と声をかけ、一緒に考えながら手助けをします。
2. 「いる・いらない」の判断を一緒にトレーニング
片付けの重要なステップの一つが、モノの要不要の判断です。これは大人でも難しいと感じることがあります。
- 「いる・いらない・迷う」の3つのボックス: 定期的にモノを見直す際、「いる」「いらない」「迷う」の3つのボックスを用意し、子どもと一緒にモノを分類する練習をしましょう。「これはまだ遊ぶかな?」「これはもう使わない?」と優しく問いかけ、子どもの判断を尊重します。
- 判断基準を伝える: 「これは壊れているから、もう使えないね」「もう小さくなったから、他の子にあげたら喜ぶかな?」など、判断のヒントを具体的に伝えます。
- 「迷う」ボックスの活用: 「迷う」ボックスに入れたものは、しばらく保管しておき、期間を決めてもう一度見直します。そうすることで、衝動的に捨てることを防ぎ、本当に必要なモノを見極める力を養います。
3. 「分類する」力を一緒に育む
モノを適切に分類することは、整理整頓の基本です。
- 「仲間分け」ゲーム: 最初は「乗り物のおもちゃはここ、人形のおもちゃはここ」というように、簡単なカテゴリーから始めます。「これは何の仲間かな?」と、クイズ形式で楽しく分類する練習をするのも良いでしょう。
- ボックスの活用: 透明なボックスや、ラベル付きのボックスを使って、分類が視覚的に分かりやすい収納を心がけましょう。
4. 片付けの「手順」を一緒に確認する
「片付けなさい」という漠然とした指示ではなく、具体的な手順を一緒に確認することで、子どもは安心して取り組めます。
- ステップ化: 例えば、「①おもちゃを全部出す→②いるものといらないものを分ける→③きれいに拭く→④定位置に戻す」のように、片付けの工程を分解して伝えます。
- チェックリストの活用: 慣れてきたら、簡単なイラスト付きのチェックリストを作り、片付けが終わったらチェックを入れるなど、ゲーム感覚で楽しむ工夫も有効です。
親が「一緒に」関わることで、子どもは片付けを「やらされること」ではなく、「親と一緒にやる楽しいこと」と捉えるようになります。
この「一緒に」という言葉の魔法をぜひ活用してみてください。
子どもでも続けやすいルール・収納アイデアとは

子どもが片付けを続けるためには、シンプルで分かりやすいルールと、使いやすい収納が必要です。
リラックスできるすっきりとした空間を保つためにも、ぜひ参考にしてみてください。
1. シンプルで分かりやすいルール作り
- ルールは少数精鋭で: たくさんのルールは子どもを混乱させ、やる気をなくさせます。まずは「一つ出したら一つしまう」「寝る前は必ずリビングを片付ける」など、最も守ってほしいルールを2~3つに絞りましょう。
- 視覚化する: ルールを紙に書き出し、イラストを添えて、子ども部屋やリビングなど、いつも目につく場所に貼っておくと効果的です。文字が読めない幼児期は、イラストだけでも十分です。
- 「○○しないと✕✕になる」ではなく「○○すると△△になる」: ポジティブな言葉でルールを伝えます。「片付けないと遊べない」ではなく、「片付けたら、もっと広く遊べるね!」といった声かけを意識しましょう。
- 家族で決める: 親が一方的に決めるのではなく、子どもも参加してルールを決めることで、「自分たちのルール」という意識が芽生え、守ろうという気持ちにつながります。
2. 片付けが楽になる収納アイデア
- オープン収納を活用する: 扉や引き戸があると、子どもにとっては手間が増え、出し入れが億劫になります。棚やカラーボックスなど、オープンな収納をメインにすることで、片付けのハードルが下がります。
- ボックス収納で「ポイポイ収納」を可能に: おもちゃや小物類は、種類ごとにボックスを用意し、そこに入れるだけで片付けが終わる「ポイポイ収納」がおすすめです。
- 透明なボックス: 中身が見えるため、どこに何があるか一目で分かり、探す手間が省けます。
- キャスター付きボックス: 遊ぶ場所まで簡単に移動でき、遊び終わったら元の場所に戻しやすいです。
- ラベリングを徹底: 写真やイラスト付きのラベルを貼ることで、文字が読めない子どもでも、どこに何をしまうべきか迷いません。
- 定位置+一時置き場: 全てのモノに完璧な定位置を作るのは難しい場合もあります。一時的に置ける「とりあえずボックス」などを設置し、ある程度溜まったら一緒に整理する、というルールも有効です。ただし、このボックスが散らかりの温床にならないよう、定期的な見直しが必要です。
- ランドセル置き場を玄関近くに: 学校から帰ってきてすぐにリビングに放り投げられることが多いランドセル。玄関に近い場所に専用の置き場(ランドセルラックやフックなど)を用意することで、部屋に持ち込む前に片付ける習慣をつけやすくなります。
- プリント・書類は専用の収納を: 学校からのプリントや提出物など、重要な書類は散らかりやすいモノの一つです。専用のファイルボックスやトレーを用意し、「ここに入れるだけ」というシンプルなルールを作ることで、紛失を防ぎ、散らかることを防ぎます。
- 「床に直置きしない」を徹底: 床にモノが散らかっていると、掃除もしにくくなりますし、見た目もごちゃごちゃします。まずは「床には何も置かない」という意識を親子で持つことが大切です。簡単なフックやS字フックを活用して、一時的にでも吊るせる場所を作るのも有効です。
これらのルールや収納アイデアは、親の負担を減らし、子どもが自主的に片付けに取り組むための「土台」となります。無理なく、楽しみながら取り入れられるものから始めてみましょう。
片付けを楽しく!我が家で効果があった神アイデア7選

「片付けは嫌なもの」というイメージを払拭し、子どもが自ら楽しく片付けに取り組めるようになるには、親のちょっとした工夫が大切です。
ここでは、我が家で実際に効果があった「神アイデア」を7つご紹介します。
1. おもちゃやモノごとの分類・ボックス収納で迷わない環境づくり
子どもが片付けられない大きな理由の一つが、「どこに何をしまえばいいか分からない」ことです。
これを解消するためには、徹底した分類と、使いやすいボックス収納が不可欠です。
- モノの種類ごとに分類する:
- レゴブロック、積み木、ミニカー、人形、パズルなど、おもちゃを種類ごとに大きく分類します。
- 文房具も鉛筆、消しゴム、クレヨン、ハサミなど、細かく分けて収納場所を決めましょう。
- 専用のボックスを用意する:
- 分類したおもちゃごとに、それぞれ専用のボックスを用意します。サイズや色を揃えると、見た目もすっきりします。
- 我が家では: 100円ショップの収納ケースや、IKEAのTROFAST(トロファスト)のような、子どもでも扱いやすい引き出し式の収納を組み合わせました。
- 写真やイラストでラベリング:
- 特に文字が読めない幼児や、整理が苦手な小学生には、ボックスのフタや側面に、中身のモノの写真やイラストを貼るラベリングが非常に効果的です。
- 我が家では: 子どもと一緒に、おもちゃの写真を撮り、それを印刷してラベリングしました。自分で作ったラベルなので、子どもも愛着がわき、より積極的に片付けに取り組むようになりました。
- 「ポイポイ収納」を意識する:
- 片付けは、できるだけワンアクションで完結するのが理想です。フタを開けて、仕分けして…という手間が多いと、子どもは途中で諦めてしまいます。ボックスにポンと入れるだけで済むような、シンプルで簡単な収納を心がけましょう。
- 定位置は「子どもが決める」要素も取り入れる:
- 親が一方的に決めるのではなく、「このおもちゃは、どこにしまうのが一番使いやすいかな?」と、子どもと一緒に定位置を考える時間を作りましょう。自分で決めた場所なら、より責任感を持って片付けに取り組むようになります。
このように、モノの定位置を明確にし、視覚的に分かりやすい収納環境を整えることで、子どもは「迷うことなく」片付けられるようになり、親の「どこにしまうの!」というイライラも大きく減らすことができます。
2. 子供専用スペースや子供部屋の工夫で“自分ごと”に変える
子どもが片付けない理由の一つに、「自分だけの場所」という意識が希薄な場合があります。
子ども専用のスペースや子ども部屋を工夫することで、片付けを「自分ごと」として捉え、大切に扱う気持ちを育むことができます。
- 「マイ・スペース」を作る:
- 子ども部屋がなくても、リビングの一角に子ども専用の「遊びコーナー」や「勉強コーナー」を設けるだけでも効果があります。専用のカーペットを敷いたり、小さな棚を置いたりするだけで、「ここは私の場所」という意識が芽生えます。
- 我が家では: リビングの隅に小さなプレイマットを敷き、そこが「おもちゃの家」と決めました。その範囲で遊ぶ、その範囲で片付ける、というルールを自然と意識できるようになりました。
- 子ども部屋のレイアウトを一緒に考える:
- 小学生になると、自分の部屋を持つ子も多いでしょう。この機会に、子どもの意見を取り入れながら、部屋のレイアウトを一緒に考えましょう。
- 「ベッドはここがいい」「机は窓際がいいな」など、子ども自身が居心地の良い空間を考えることで、部屋への愛着が深まり、片付けも前向きに取り組むようになります。
- 我が家では: 娘と一緒に家具の配置を決め、収納棚の色を選ぶなど、決定権を一部与えました。すると、「私の部屋だから、きれいにしたい!」という意識が強くなりました。
- 「秘密基地」のようなワクワク感を演出:
- 子どもにとって、自分の部屋やスペースは「秘密基地」のようなワクワクする場所であってほしいものです。例えば、天井にプラネタリウムのプロジェクターを置いたり、おしゃれなガーランドを飾ったりと、子どもが「大切にしたい」と思えるような工夫を凝らしてみましょう。
- 子どもの作品を飾る場所を作る:
- 学校で作った作品や、描いた絵など、子どもが大切にしているモノを飾る専用のスペースを作りましょう。作品を飾ることで、子ども部屋が「自分の居場所」という意識が強まります。また、飾るモノが増えたら定期的に見直す習慣も身につきます。
- 我が家では: 壁にワイヤーネットを取り付け、そこにクリップで作品を飾れるようにしました。作品が増えたら、古いものと入れ替える、というルールにすることで、モノの整理も自然と促されました。
子ども専用のスペースや部屋を「自分だけの特別な場所」にすることで、子どもはそこを大切にしたいと感じ、自然と片付けへのモチベーションが高まります。
親も、子どもの意見を尊重しながら、一緒に素敵な空間を作り上げていくプロセスを楽しみましょう。
3. 整理整頓をゲーム・遊び化してモチベーションUP

「片付けは面倒なこと」というイメージを、「片付けは楽しいこと」に変えるには、ゲーム感覚や遊びの要素を取り入れるのが効果的です。
特に小学生の子どもには、競争心をくすぐるアイデアや、目標達成型のゲームがおすすめです。
- タイムアタック片付けゲーム:
- 「よーいドン!で、このボックスにおもちゃを全部入れられるかな?〇分以内にできるかな?」と時間を設定して、競争するように片付けを促します。ストップウォッチを使うと、より盛り上がります。
- 我が家では: 音楽に合わせて片付けをする「お片付けミュージックタイム」を導入しました。曲が終わるまでに片付ける、というルールで、子どもたちはノリノリで片付けてくれます。
- ポイント制・ご褒美制度の導入(ただし注意が必要):
- 片付けができたらポイントを付与し、一定のポイントが貯まったら、ちょっとしたご褒美(お菓子、好きなDVDを見る時間、絵本を一冊選ぶ権利など)を与える制度です。
- 注意点: モノで釣る形にならないよう、ご褒美は形に残らない体験型がおすすめです。また、ご褒美がなくても片付けができるようになることが最終目標なので、徐々にポイント制から卒業していく工夫も必要です。
- 我が家では: 「お片付けビンゴ」を導入しました。片付けができた項目にシールを貼り、ビンゴになったら家族で外食、というご褒美を設定しました。達成感と家族での楽しみが結びつき、モチベーション維持に役立ちました。
- 「どこに帰る?」クイズ:
- 散らばったモノを一つ手に取り、「これはどこに帰るお家だったかな?」とクイズ形式で子どもに尋ねます。正解したら拍手してあげるなど、盛り上げると良いでしょう。
- 我が家では: モノの定位置が分からなくなった時や、少しマンネリを感じた時にこのクイズを取り入れました。特に低学年の子どもには、楽しく学べる良い機会になりました。
- お片付けソングを作る:
- 家族でオリジナルの片付けソングを作って歌いながら片付けをするのも楽しいアイデアです。歌詞に、それぞれのモノの定位置を盛り込むのも良いでしょう。
- 「片付けリレー」で家族と協力:
- 家族でバトンを渡すように、「ママがここを片付けたから、次はパパがここ、その次はお子さんがここ!」と役割を交代しながら片付けるリレー形式のゲームです。協力して一つの目標を達成する喜びを味わえます。
片付けをゲームや遊びにすることで、「やらされている」という感覚がなくなり、子どもは自ら進んで片付けに取り組むようになります。
大切なのは、親も一緒に楽しみ、成功体験を共有することです。
4. プリントや教科書は専用収納を用意、時間と手間を削減
小学生になると、学校からのプリントや教科書、宿題の持ち物など、紙類が格段に増えます。
これらが散らかる原因となり、片付けのストレスになることも少なくありません。専用の収納を用意することで、時間と手間を削減し、子ども自身で管理できる仕組みを作りましょう。
- ランドセルラックと連携した収納:
- 学校から帰ってきて、まずランドセルを置く場所の近くに、教科書やプリントを一時的に置けるスペースを設けるのが効率的です。
- 我が家では: ランドセルラックの横に、A4サイズのファイルボックスをいくつか並べました。「今日の宿題」「提出物」「明日の準備」「重要プリント」など、ラベリングをして分類できるようにしました。
- 「投函ボックス」で一時保管:
- 親が確認する必要のあるプリントや、提出期限が近いプリントは、一時的に「投函ボックス」のような専用の箱を用意しておくと便利です。子どもはそこにポンと入れるだけで良く、親は後でまとめて確認できます。
- 我が家では: キッチンカウンターの隅に、おしゃれな木製の箱を置き、「お便りボックス」と名付けました。重要な書類を見落とすことが減り、子どもも迷わず入れられるようになりました。
- 教科書・ノートは科目ごとに分類:
- 教科書やノートは、科目ごとに立てて収納できるファイルボックスやブックエンドを活用します。取り出しやすく、戻しやすい工夫が大切です。
- 我が家では: カラーボックスに科目ごとのファイルボックスを入れ、それぞれに科目の名前を大きく書いたラベルを貼りました。子どもが授業で使うものを自分で選び、戻せるようになりました。
- 宿題・明日の準備セットをまとめる:
- 宿題で使う文房具や、明日の持ち物(体操服、給食着など)は、一箇所にまとめておける専用のボックスや引き出しを用意すると、準備がスムーズになります。
- 我が家では: 翌日の時間割と持ち物をチェックするスペースを机の上に作り、その日のうちに翌日の準備を完了させる習慣をつけました。忘れ物が減り、朝のバタバタも解消されました。
- 不要なプリントは定期的に処分:
- たまりがちなプリント類は、親が積極的に声かけし、子どもと一緒に定期的に見直して不要なものは処分する習慣をつけましょう。シュレッダーをかける作業を子どもに手伝ってもらうのも、モノの処分への意識を高める良い機会になります。
紙類の収納を工夫することで、部屋が散らかるのを防ぐだけでなく、子どもの学習効率も上がります。親のイライラも減り、親子で気持ちよく過ごせるようになるでしょう。
5. 家族全員参加型のルール作りで片付けを“家族の習慣”に
片付けは、子どもだけの責任ではありません。家族全員が協力し、片付けを「家族の習慣」として定着させることが、成功への近道です。
子どもを巻き込み、主体的にルール作りに参加させることで、やる気を引き出すことができます。
- 「家族会議」でルールを決める:
- 月に一度、または必要に応じて「家族会議」を開き、片付けに関するルールを話し合いましょう。
- 「リビングがいつも散らかっているのはなぜだろう?」「どうすればみんなが気持ちよく過ごせるかな?」といった問いかけから始め、子どもにも意見を出してもらいます。
- 我が家では: 家族会議で「リビングのおもちゃは、寝る前に必ずおもちゃ箱に戻す」「各自の私物は、専用のボックスに入れる」といった簡単なルールを決めました。子ども自身が考えたルールなので、守ろうという意識が強くなりました。
- ルールを可視化する:
- 決まったルールは、リビングの壁など、家族みんなが目にする場所に貼っておきましょう。イラストを添えたり、カラフルなペンを使ったりして、子どもが見て楽しい工夫を凝らすと良いでしょう。
- 我が家では: 家族の似顔絵とともにルールを書き出し、マグネットボードに貼りました。ルールを破ってしまった時は、感情的に叱るのではなく、「ルール、見てみようか」とボードを指差すだけで、子どもも納得しやすくなりました。
- 当番制を取り入れる:
- 家族それぞれに片付けの当番を決めるのも良い方法です。「今日はリビングの片付け当番は〇〇ちゃん」「食卓をきれいにするのはパパの当番」など、役割を明確にすることで、責任感が生まれます。
- 我が家では: 曜日ごとに担当を決めて、おもちゃの片付けや、食卓の拭き掃除などを担当してもらいました。自分の番が回ってくると、「今日は僕の番だ!」と張り切って取り組んでくれるようになりました。
- 親も「片付け名人」に:
- 子どもは親の行動をよく見ています。親自身が、自分のモノを整理整頓し、散らかさないように意識することで、子どもにとっての良い手本となります。
- 「いつもママが頑張っているから、私も頑張ろう」と、子どもは自然と感じるようになります。
- 協力し合う姿勢を見せる:
- 誰かが困っている時には、「手伝おうか?」と声をかけ、家族で協力し合う姿勢を見せることが大切です。片付けは一人でやるものではなく、家族みんなで協力して作り上げるもの、という意識を育みましょう。
片付けを「家族の習慣」にすることで、家庭全体の生活の質が向上し、親のイライラも減り、家族みんなが笑顔で過ごせる時間が増えるでしょう。
6. 小学生~中学生・高校生まで年齢別対策と声かけのコツ

子どもの成長とともに、片付けに対するアプローチも変えていく必要があります。
小学生だけでなく、中学生、高校生と年齢が上がるにつれて、声かけの仕方やサポートの仕方も工夫していきましょう。
小学生(低学年):具体的で視覚的なサポートが中心
- 特徴: まだ抽象的な思考が苦手で、指示は具体的であるほど理解しやすい。遊びへの関心が大きく、集中力はまだ短い。
- 対策:
- 徹底したモノの定位置化とラベリング: 写真やイラスト付きのラベルで、どこに何をしまうか一目でわかるようにします。
- ゲーム感覚を取り入れる: タイムアタックやポイント制など、遊びの要素を取り入れて楽しく片付けを促します。
- 「一緒」に片付ける時間を作る: 親が手本を見せながら、一緒に片付けを行います。
- 達成したらすぐに褒める: 小さなことでも「よくできたね!」「ありがとう!」と具体的に褒めることで、やる気を引き出します。
- 声かけのコツ: 「このブロック、ここがお家だよ。帰してあげられるかな?」「ママがここを拭くから、〇〇ちゃんはこの絵本を棚に戻してね。」
小学生(高学年):自立を促し、メリットを伝える
- 特徴: 自分で考え、判断する力が育ち始める。論理的な思考もできるようになるため、片付けのメリットを理解できる。友達との関係や自分の時間を重視し始める。
- 対策:
・片付けの「必要性」を共有する:「部屋がきれいだと探し物がすぐ見つかって、自分の時間が増えるよ」「友達が遊びに来た時に気持ち良いね」など、片付けのメリットを具体的に伝えます。
・「自分専用」のスペースを尊重する: 子ども部屋があれば、ある程度の片付けは本人に任せ、過度に干渉しないようにします。ただし、リビングなどの共有スペースは家族のルールを徹底させます。
・モノの見直しを一緒に:成長に伴い不要になったモノを、子ども自身が「いる・いらない」を判断できるよう促します。フリマアプリに出したり、寄付したりするなど、社会とのつながりも意識させると良いでしょう。
- 声かけのコツ: 「そろそろテスト前だから、机の上を片付けて集中できる環境を作らない?」「自分で片付けられたら、もっとゲームする時間が増えるかもね。」
中学生・高校生:自律を尊重し、責任感を育む
- 特徴: 思春期を迎え、親からの干渉を嫌がる傾向が強まる。自分の世界を大切にする。テスト勉強や部活動など、多忙になる。
- 対策:
- 「自分で決める」機会を増やす: 片付けのルールや収納方法など、子ども自身に決めさせる部分を増やします。親はあくまで「相談役」としてサポートに回ります。
- 共有スペースのルールは徹底: 子ども部屋は個人の空間として尊重しつつ、リビングやダイニングなどの共有スペースは、家族としてのルールをきちんと守ってもらいます。
- 片付けないことによる「不便さ」を体験させる: 忘れ物が増える、探し物が見つからないなど、片付けないことによる不便さを子ども自身に体験させることで、自分で片付けの必要性を感じるように促します。ただし、感情的に叱るのではなく、淡々と事実を伝えることが重要です。
- 生活全体の中での整理整頓の重要性を伝える: 受験勉強や将来の生活に目を向けさせ、計画的に物事を整理する力を養うことの重要性を伝えます。
- 声かけのコツ: 「部屋が散らかっていると、集中できないんじゃない?」「提出物、ちゃんと確認した?」「何か手伝うことある?」
年齢が上がるにつれて、親は「指示する」立場から「見守る」「サポートする」立場へとシフトしていくことが大切です。
子どもの成長を信じ、適切な距離感を保ちながら、片付けの習慣化を応援していきましょう。
7. 片付けタイムの明確化と成果をほめる言葉の魔法
片付けを習慣化し、子どものやる気を引き出すためには、「いつ片付けるのか」を明確にし、片付けられた「成果」を適切に褒めることが非常に重要です。
「片付けタイム」を明確にする
- 「〇時になったら片付け」: 遊び始める前に「〇時になったら片付けタイムだよ」と事前に伝えることで、子どもは心の準備ができます。時間になったらアラームを鳴らすのも効果的です。
- 「寝る前〇分」: 夜寝る前に、部屋やリビングを「〇分だけ片付けよう」と時間を決めて取り組むのも習慣化に繋がります。
- 「帰宅後すぐ」: 学校から帰ってきたら、まずランドセルを所定の位置に戻し、中身を整理する、というルーティンも有効です。
- 我が家では: 「夕食前10分はお片付けタイム」と決めました。タイマーをセットし、タイマーが鳴るまでにどれだけ片付けられるか、というゲーム感覚で取り組んでいます。
「成果をほめる」言葉の魔法
- 具体的に褒める: 「すごいね!」だけでなく、「ブロックが全部箱にきれいに収まっているね!」「絵本がきちんと棚に並んでいると、読みやすいね!」など、具体的にどこがどう良かったのかを伝えましょう。
- 努力の過程を褒める: たとえ完璧でなくても、「片付けを始めようとしたんだね、えらいね!」「最後まで頑張って片付けたね!」と、片付けに取り組んだ「努力の過程」を褒めることが大切です。
- 感謝の気持ちを伝える: 「部屋がきれいになって、ママも嬉しいよ、ありがとう!」「探し物がすぐ見つかって、助かったよ!」と、感謝の気持ちを伝えることで、子どもは「自分の行動が役に立った」と感じ、自己肯定感が高まります。
- 「成長」を伝える: 「前はここまでできなかったのに、自分でできるようになったね!」と、過去と比較して子どもの成長を伝えることで、自信につながります。
- 我が家では: 片付けが終わったら、家族みんなで「きれいになったね!」と確認し合い、ハイタッチをしたり、「ありがとう!」と感謝の言葉を伝え合うようにしています。これにより、片付けがポジティブな行動として子どもにインプットされるようになりました。
片付けタイムを明確にし、メリハリをつけることで、子どもは「いつ、何をすれば良いか」を理解しやすくなります。
そして、片付けられた成果を具体的に褒め、感謝の気持ちを伝えることで、子どもは「また頑張ろう!」というモチベーションを維持し、自ら片付けに取り組む「やる気」を育むことができるでしょう。
発達障害や苦手な子への具体的な片付けサポート方法

発達障害の特性を持つ子どもや、他の子に比べて極端に片付けが苦手な子どもには、よりきめ細やかなサポートと環境調整が必要です。
できないことを叱るのではなく、特性を理解し、その子に合った方法で支援することが大切です。
発達障害がある子供への具体的な片付け対策・環境調整
発達障害のある子どもは、脳の特性上、片付けに必要なスキル(計画性、注意の維持、物の分類、空間認識など)が苦手な場合があります。
そのため、親は「できないことをできるようにさせる」のではなく、「できない部分を補うための環境調整」と「具体的なサポート」に焦点を当てる必要があります。
1. 視覚的な情報を徹底する
言葉での指示は理解しにくい場合があるため、視覚的な情報を取り入れることが最も重要です。
- 写真・イラストでのラベリング: ボックスの中身を示すラベルは、文字ではなく写真やイラストを使います。
- 色分け収納: 「赤い箱にはブロック」「青い箱には車」のように、色で分類を明確にします。
- 片付け手順の視覚化: 片付けのステップを、イラスト付きのボードやチェックリストにして、目につく場所に貼っておきます。「①おもちゃを出す→②分類する→③箱に入れる→④棚に戻す」のように、シンプルに分解して示します。
- 透明な収納ボックスの活用: 中身が見える収納ボックスを使うことで、「何がどこにあるか」が一目で分かります。
2. シンプルな収納とモノの定位置の徹底
- 収納スペースの削減: モノが多いと混乱するため、必要最低限のモノに絞り、シンプルな収納を心がけます。
- 定位置を一つだけにする: 「このおもちゃはここ!」と、定位置を一つに決め、複数の場所を設けません。
- 「ポイポイ収納」の導入: 複雑な仕切りや細かい分類は避け、大きなボックスにざっくり入れられる「ポイポイ収納」が効果的です。
3. スケジュールとルーティンを明確にする
- 片付け時間の固定化: 「毎日〇時に片付けタイム」と時間を決め、ルーティン化します。視覚的なタイマー(砂時計や残り時間が色で表示されるタイマー)を使うと、時間の見通しがつきやすくなります。
- 直前の声かけと確認: 片付けの少し前に「あと〇分で片付けだよ」と声かけし、片付けを始める直前にも「何から片付ける?」と確認することで、切り替えをサポートします。

4. 感覚過敏への配慮
- 触感・音への配慮: 物の触感や音が苦手な場合は、柔らかい素材の収納を選ぶ、音が響きにくい場所に収納するなど、感覚的な刺激を減らす工夫をします。
- ごちゃごちゃ感を減らす: モノが多いと視覚的な刺激が強くなり、混乱しやすいため、全体的にすっきりとした環境を保つようにします。
5. 成功体験を積み重ね、具体的に褒める
- 小さな目標設定: 「このブロックを10個箱に入れる」など、ごく小さな目標を設定し、達成感を味わわせます。
- 具体的に褒める: 「ブロックを全部箱に入れることができたね、すごいね!」と、できたことを具体的に褒め、成功体験を積み重ねさせます。
6. 専門家との連携
- もし片付け以外の面でも気になる特性がある場合は、専門家(医師、作業療法士、発達支援コーディネーターなど)に相談し、適切なアドバイスや支援を受けることが大切です。
- 専門家は、子どもの特性に合わせた具体的なアプローチ方法を提案してくれます。
発達障害のある子どもへの片付けサポートは、一朝一夕にはいきません。親が特性を理解し、根気強く、愛情を持って関わることが、子どもの成長を大きく後押しします。
できないことを叱らず伸ばす!苦手克服を支援する親の関わり方

発達障害の有無に関わらず、片付けが苦手な子どもに対しては、「できないことを叱る」のではなく、「どうすればできるようになるか」という視点でサポートしていくことが大切です。
親の関わり方一つで、子どものやる気や自己肯定感は大きく変わります。
1. 叱るよりも「なぜできないのか」を理解する
- 子どもが片付けられない時、感情的に「どうしてできないの!」と叱ってしまう前に、「どこで困っているんだろう?」「何が難しいのかな?」と、子どもの視点に立って考えるようにしましょう。
- 理由が分からない場合は、直接子どもに「どこが難しい?」と優しく尋ねてみるのも良いでしょう。
2. スモールステップで「できる」を積み重ねる
- 一度に全てを片付けさせようとせず、非常に小さなステップに分解して指示を出します。
- 例:「まず、このブロックを一つだけ箱に入れようか。」
- 「次に、この絵本を棚に戻してみようか。」
- 一つ一つのステップがクリアできたら、「できたね!すごい!」とすぐに褒め、達成感を味合わせます。
3. ポジティブな言葉かけと励まし
- 「ありがとう!助かったよ!」「〇〇が片付けてくれたおかげで、部屋がすっきりしたね!」と、感謝や具体的な喜びの気持ちを伝えます。
- 失敗しても、「大丈夫、次は一緒にやってみようね」「ちょっと難しかったかな?どこから手伝おうか?」と、前向きな言葉で励まします。
- 子どもの努力の過程を認め、「頑張ったね」と声をかけることで、次への意欲につながります。

4. 比較しない、競争させない
- 他の子や兄弟姉妹と片付けの能力を比較することは、子どもの劣等感を刺激し、自己肯定感を低下させます。「あなたはあなたで頑張ればいいんだよ」というメッセージを常に伝えましょう。
- 競争させるのではなく、子ども自身の過去と現在を比較し、「前よりできるようになったね!」と成長を伝えるようにしましょう。
5. 親も完璧を求めすぎない
- 親自身が「完璧に片付いていなければならない」という思い込みを手放し、ある程度の「許容範囲」を持つことが大切です。
- 「今日はこれだけできればOK」という柔軟な姿勢で臨むことで、親自身のイライラも軽減されます。
6. 成功体験を記録する
- 片付けができた日や、特に頑張った片付けがあった日に、シールを貼るカレンダーや、簡単な記録帳などを作成するのも良いでしょう。
- 目に見える形で成功体験を記録することで、子どもは自分の成長を実感し、やる気を継続させやすくなります。
苦手なことを克服するには、時間がかかります。親が焦らず、子どものペースに寄り添い、小さな成長を見逃さずに褒め、励まし続けることで、子どもは自信を持ち、少しずつ「できること」を増やしていくことができるでしょう。
子供の片付け習慣を定着させるために親ができる工夫とQ&A

片付けは、一度できるようになれば終わり、というものではありません。子どもの成長に合わせて、習慣として定着させていくための工夫が必要です。
ここでは、親ができる継続的なサポートと、よくある悩みに対するQ&Aをご紹介します。
子どもの成長過程と片付け力の伸ばし方
子どもの片付け能力は、成長とともに変化していきます。それぞれの発達段階に合わせたアプローチで、無理なく片付け力を伸ばしていきましょう。
1. 幼児期(〜小学校入学前):遊びの延長で楽しく

- 特徴: 「ごっこ遊び」が好きで、模倣しながら学ぶ。集中力は短く、親との共同作業を好む。
- 伸ばし方:
- 「おもちゃさん、お家に帰ろうね」: モノを擬人化し、遊びの延長で片付けを促します。
- 親が手本を見せる: 親が楽しそうに片付けている姿を見せることで、子どもも自然と真似をするようになります。
- シンプルな収納: 大きなボックスにざっくり入れられる収納を用意し、まずは「しまう」という行動自体を習慣化します。
- 達成感を共有: 片付けができたら、「できたね!きれいになったね!」と、一緒に喜びを分かち合います。
2. 小学校低学年(1年生〜3年生):視覚的な指示とスモールステップ

- 特徴: 指示を具体的に理解できるようになるが、抽象的な思考は苦手。遊びへの関心が強く、飽きやすい。
- 伸ばし方:
- 視覚的なラベリング: 写真やイラスト付きのラベルで、どこに何をしまうかを明確にします。
- 片付けの手順を可視化: 簡単なイラスト付きのチェックリストを作り、一つずつクリアしていく喜びを味合わせます。
- 「一緒にやる」を基本に: 親が付き添い、具体的な指示を出しながら、一緒に片付けを行います。
- 時間制限を設ける: 「あと5分で片付けようね」と伝え、タイマーを使うなどして、時間の見通しを持たせます。
3. 小学校高学年(4年生〜6年生):自律を促し、メリットを伝える

- 特徴: 論理的な思考力や計画性が発達し始める。自分の意見を持ち、親からの指示を嫌がることも。
- 伸ばし方:
- 片付けの「必要性」を共有する: 「部屋がきれいだと探し物が見つかりやすくて、自分の時間が増えるよ」「友達を呼びやすいね」など、片付けのメリットを具体的に伝えます。
- 自分で収納方法を考えさせる: 「ここには何をしまいたい?」「どうすれば使いやすいかな?」と、子ども自身に収納の工夫を考えさせます。
- 共有スペースのルールは徹底: 子ども部屋は個人の空間として尊重しつつ、リビングなど共有スペースの片付けルールは、家族全員で守ることを明確にします。
- モノの要不要判断をサポート: 定期的にモノを見直し、「いる・いらない」の判断を一緒に考え、必要であれば手伝います。
4. 中学生・高校生:自己管理能力の育成と責任感

- 特徴: 思春期に入り、親からの干渉を避けがち。自分の世界を確立していく時期。
- 伸ばし方:
- 「自己管理」を促す: 片付けは「自分の責任」であることを意識させます。忘れ物や探し物など、片付けないことによる不便さを自分で体験させる機会も必要です。
- 共有スペースのルールは厳守: 子ども部屋は個人の空間として尊重しつつ、共有スペースを散らかした場合は、きちんと片付けるように促します。
- 生活全体の中での整理整頓の重要性を伝える: 受験勉強や将来の自立を見据え、「計画的に整理する力」が社会で必要となることを伝えます。
- 必要に応じてサポートを申し出る: 「何か困っていることある?手伝おうか?」と、あくまでサポートの姿勢で声をかけるようにしましょう。
子どもの成長段階に合わせた適切なサポートを続けることで、片付けは「親に言われてやるもの」から「自分に必要なこと」へと意識が変化し、一生モノの習慣として定着していくことでしょう。
親子・家族・先生で“片づけ”を応援するには?役割分担の工夫

片付けの習慣化は、子ども一人では難しいものです。親子だけでなく、家族全員、そして場合によっては学校の先生も巻き込み、チームとして子どもを応援する体制を整えることが大切です。
1. 親の役割:ガイドとサポーター
- 片付けの「仕組み作り」: 子どもが片付けやすい収納環境を整え、シンプルなルール作りを主導します。
- 「一緒にやる」の継続: 成長段階に応じて、一緒に片付ける時間を設け、具体的な方法を教えていきます。
- ポジティブな声かけ: できたことを具体的に褒め、子どものやる気を引き出します。イライラしても感情的にならず、子どもの気持ちに寄り添うことを心がけます。
- 見守る姿勢: 成長するにつれて、少しずつ子どもの自主性に任せる部分を増やし、必要な時にサポートに回ります。
- 定期的な見直し: 収納やルールが子どもの成長に合っているか、定期的に親子で話し合い、改善していきます。
2. 家族(兄弟姉妹・祖父母など)の役割:協力者と理解者
- 協力し合う姿勢: 兄弟姉妹がいる場合は、互いの部屋の片付けを手伝い合ったり、リビングの片付けを協力して行うなど、チームワークを育みます。
- 理解と応援: 「うちの子は片付けが苦手だから…」と否定的に見るのではなく、「頑張っているね!」と温かく見守り、応援する姿勢で接します。
- 共通ルールの遵守: リビングなど共有スペースの片付けルールは、家族全員が守ることで、子どもも納得して取り組めます。
- 祖父母の協力: 孫におもちゃなどをプレゼントする際は、「収納スペースに入るかな?」など、親と事前に相談してもらうことで、モノが増えすぎるのを防ぎます。
3. 学校の先生の役割:生活指導の一環として
- 学校での整理整頓の指導: 教室のロッカーや机の中、持ち物の整理整頓など、学校生活の中で先生が整理整頓の重要性を指導することは、家庭での片付けにも良い影響を与えます。
- 家庭との連携(必要な場合): もし子どもが学校でも持ち物の整理が極端に苦手な場合、担任の先生に相談し、家庭での取り組みを伝えることで、学校でのサポートや、情報共有がスムーズになります。
- 「連絡帳」の活用: 忘れ物が多い、提出物がいつも出せないなど、片付けに関連する困りごとがある場合、連絡帳などを通じて先生と情報を共有し、家庭と学校で一貫した対応を考えることができます。
片付けは「家庭での教育」という側面だけでなく、「生活スキル」として社会で生きていく上で非常に大切な力です。
親子、家族、そして学校の先生といった周囲の大人たちが一丸となって子どもを応援することで、子どもは安心して片付けに取り組むことができ、その力を大きく伸ばしていくことができるでしょう。
よくある悩み・質問に答えるQ&A(捨てた・叱った・続かない…)

片付けをめぐる悩みは尽きません。ここでは、親御さんからよく聞かれる質問にお答えします。
Q1: 「片付けないから捨てた」と言ってしまい、子どもを傷つけてしまいました。どうすればいいですか?
A: まずは、正直に「あの時、ママ(パパ)もイライラしてしまって、傷つけるようなことを言ってごめんね」と謝りましょう。
そして、「本当は、あなたの大切なものを勝手に捨てるつもりはなかったんだよ」と、本当の気持ちを伝えてください。
その上で、「今後は、モノを捨てる時は、必ず一緒に確認するようにしようね」と、今後の具体的なルールを話し合うことが大切です。
大切なのは、親が自分の感情的な行動を認め、子どもとの信頼関係を修復しようとすることです。
Q2: 毎回「片付けなさい!」と叱ってばかりで、私自身も疲れてしまいます。どうしたら叱らずに済みますか?
A: 叱る回数を減らすためには、まず「叱ってしまう原因」を見つめ直しましょう。
- 期待値を下げる: 「完璧に片付かなくてもOK」という心構えを持ち、多少の散らかりは許容する練習をしましょう。
- 環境整備を優先: 子どもが片付けやすい収納環境が整っていますか?モノが多すぎませんか?叱る前に、物理的な環境を見直すことが先決です。
- 声かけを変える: 叱る言葉ではなく、「〇〇(モノの名前)はどこにお家かな?」「〇〇ちゃんが片付けてくれたら、ママ助かるな」など、ポジティブで具体的な言葉かけに変えてみましょう。
- 「一緒にやる」を基本に: 親が一人で抱え込まず、一緒に片付けに取り組むことで、叱る必要が減ります。
- 親自身のストレスケア: 親が心に余裕を持つことで、イライラを抑え、冷静に対応できるようになります。
Q3: 一時的には片付けをするのですが、すぐに散らかってしまい、習慣として続きません。どうしたら定着しますか?
A: 片付けを習慣化するには、時間がかかります。焦らず、以下の点を試してみてください。
- ルーティン化の徹底: 「寝る前5分は片付けタイム」「食卓を拭くのは〇〇ちゃんの担当」など、具体的な時間を決めて、毎日継続させることが重要です。歯磨きと同じように、生活の一部に組み込みましょう。
- 飽きさせない工夫: ゲーム要素を取り入れたり、時にはご褒美(体験型のもの)を用意したりと、飽きさせない工夫を凝らしましょう。
- 定期的な見直し: 収納方法やルールが子どもの成長やモノの量に合っているか、定期的に親子で話し合い、改善していくことが大切です。
- 小さな成功体験の積み重ね: 完璧を求めず、小さなことでも「できたね!」と褒め続け、達成感を味合わせることがモチベーション維持に繋がります。
- 「やりっぱなし」にさせない工夫: 一つ遊び終わったら、次の遊びに移る前に片付ける、というワンアクションを意識させる声かけを継続しましょう。
Q4: 片付けをしない子どもに、どのくらいの頻度で声かけをするのが適切ですか?しつこいと思われたくないです。
A: 理想は、子どもが自分で気づいて片付けることですが、それが難しい場合は、以下の点を意識しましょう。
- 「予告」と「リマインド」: 遊び始める前に「〇時には片付けタイムだよ」と予告し、時間になったら「もうすぐ片付けの時間だよ」とリマインドする、という2段階の声かけが効果的です。
- 感情的にならない: 何度も声をかけることになっても、感情的にならず、淡々と、しかし毅然とした態度で伝えましょう。
- 具体的な指示: 「片付けなさい」ではなく、「このブロックを箱に戻してね」と具体的な行動を促します。
- 片付けをサポートする: どうしても動けない時には、「ママも一緒に手伝おうか?」と声をかけ、一緒に取り組むことで、子どもも動けるようになります。
- 頻度を減らす工夫: 片付けやすい環境を整えたり、ゲーム化したりすることで、声かけの頻度自体を減らす工夫も重要です。
イライラから卒業!小学生の片付けを応援しよう

小学生の子どもが片付けないことにイライラしてしまう気持ち、本当に良く分かります。
しかし、今日ご紹介したように、子どもたちが片付けないのには理由があり、そして、親のイライラを減らすためのたくさんの工夫やアイデアがあるのです。
大切なのは、「叱ってやらせる」のではなく、「どうすれば子どもが自ら片付けたくなるか」という視点を持つこと。そして、親自身がその気持ちに寄り添い、一緒に考え、応援し続けることです。
- 子どもの気持ちと行動を理解する: 発達段階や性格、モノの量など、片付けない理由を理解することが第一歩です。
- 親のイライラの原因を見つめ直す: 完璧主義を手放し、子どもへの期待値を調整するなど、親自身の心のケアも大切です。
- 具体的な環境を整える: モノの定位置を決め、視覚的に分かりやすい収納を作り、子どもが片付けやすい仕組みを整えましょう。
- 楽しく習慣化する工夫を取り入れる: ゲーム感覚を取り入れたり、「一緒」に片付けたりすることで、片付けをポジティブな行動に変えていきましょう。
- 成果を認め、具体的に褒める: 子どもが片付けに取り組んだ努力や、できたことに対して、感謝と褒め言葉を惜しまないでください。
片付けは、子どもが社会で生きていく上で大切な「自己管理能力」を育むことにもつながります。
家族みんなが笑顔で過ごせる、すっきりとした心地よい空間を、ぜひ親子で一緒に作り上げていってください。
イライラから卒業し、お子さんの片付けを温かい目で見守り、応援する毎日へと変わっていくことを願っています。